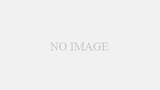スポンサードリンク
◆ 高齢者講習に「落ちる」ことはあるのか?
高齢者講習を受けるにあたり、多くの方が不安に感じているのが、「試験で落ちるのではないか?」という疑問です。
実際のところ、高齢者講習そのものには「合否」は存在しません。
講習はあくまで知識の再確認と運転能力の確認を目的としており、最後まで受ければ「修了」となります。
しかし、75歳以上の方を対象とした「認知機能検査」においては、結果によって追加の対応が必要になる場合があります。
これを誤って「落ちた」と表現されるケースが多いのです。
◆ 認知機能検査とは?再試験の発端になる重要なステップ
75歳以上の方は、免許更新の前に「認知機能検査」を受ける必要があります。
これは、認知症の恐れがあるかどうかを見極めるための簡易検査で、記憶力や時間の把握力などをチェックします。
検査項目は大きく分けて次の3つです。
◎ 時間の見当識
「今日は何年・何月・何日ですか?」
「今日は何曜日ですか?」など、現在の日付や曜日を正確に答えられるかを確認します。
◎ 記憶力検査(イラスト記憶)
複数のイラストを一定時間見せたあと、別の問題を解き、その後に「先ほど見た絵を思い出してください」と出題されます。
◎ 遅延再生(思い出し問題)
時間をおいてから、どれだけイラストを記憶しているかが試されます。
◆ 検査結果による3つの分類と講習の分かれ道
検査の結果によって、次の3つに分類されます。
■ 第1分類:認知機能低下のおそれがある
・記憶力や判断力が明らかに低下していると判定
・臨時適性検査(医師の診断)や免許更新不可の可能性も
・一部のケースでは免許返納を勧められる
■ 第2分類:認知機能低下の可能性がある
・やや判断力が低下しているとされるグレーゾーン
・通常よりも長めの「高度講習」が求められることもある
■ 第3分類:認知機能に問題なし
・記憶力・判断力ともに問題なしとされ、通常の高齢者講習を受講すればOK
◆ 「落ちた」とされるのは第1分類に該当した場合
認知機能検査で「第1分類」と判定された場合、多くの方が「落ちた」と感じることになります。
この判定に該当すると、運転免許更新のために次のいずれかの対応が必要です。
◎ 医師による診断書の提出
かかりつけ医や認知症専門医による「認知症ではない」という診断が必要です。
この診断書を警察署に提出し、認められれば免許更新手続きに進めます。
◎ 臨時適性検査の受験
警察が指定する運転適性検査を受け、運転に支障がないと判断されれば更新が可能です。
◎ 自主返納を選ぶ
認知症の疑いが濃厚な場合や、医師の診断で「認知症」とされた場合は、免許を返納することになります。
◆ 医師の診断が必要になったら?手続きの流れ
もし認知機能検査で「第1分類」と判定され、医師の診断が必要になった場合、以下のような流れになります。
【ステップ1】 検査結果通知を確認
【ステップ2】 指定医療機関またはかかりつけ医に診断を依頼
【ステップ3】 所定の書式で診断書を作成してもらう
【ステップ4】 警察署や免許センターに診断書を提出
【ステップ5】 結果通知後、更新または返納の判断
※ 診断内容によっては、追加検査やヒアリングが実施されることもあります。
◆ 「再試験」は何度でも受けられるの?
ここで注意したいのが、認知機能検査自体を再受験することはできないという点です。
一度検査を受けた結果が「第1分類」であった場合、再試験ではなく、医師の診断や臨時検査に進む必要があります。
再度認知機能検査を受けて結果を上書きすることはできません。
◆ 認知機能検査で不安な方へ:対策方法とポイント
検査は事前の準備が可能です。いくつかの対策ポイントを挙げておきます。
◎ 日常的に日付や曜日を意識する習慣をつける
「今日は何曜日?」「何月何日?」という問いかけを毎日自分にしてみましょう。
◎ 絵や図形を記憶する練習をしておく
市販の対策本やアプリ、自治体が配布している無料教材を活用し、視覚的な記憶力を鍛えましょう。
◎ 十分な睡眠と体調管理
検査当日は緊張や寝不足が悪影響を及ぼすことがあります。
特に午前中の検査は前夜の準備がカギです。
◆ 家族ができるサポートとは?
高齢者講習や認知機能検査は、高齢ドライバー本人にとって大きな負担です。
家族がそばにいてサポートすることが、精神的な安定にもつながります。
・講習予約のサポート
・検査内容の予習を一緒にする
・当日の送迎や付き添い
・結果が出た後の判断支援(返納も含む)
本人の意志を尊重しながらも、安全と安心の両立を目指しましょう。
◆ 免許を失っても不便を最小限にする工夫
仮に認知機能検査の結果により免許を更新できなかったとしても、移動手段を工夫すれば生活の質を維持できます。
◎ 代替交通手段を活用
・自治体のコミュニティバスや乗合タクシー
・高齢者向けの配車サービス(有料・無料あり)
・家族の送迎やシェアカー利用
◎ 買い物支援サービスの活用
最近では、ネットスーパーや移動販売車を活用して買い物に困らない地域支援も増えています。
◆ まとめ:再試験に不安を感じたら、まず正しい知識を
・高齢者講習には合否はないが、認知機能検査には分類がある
・「第1分類」=医師の診断が必要になるため、誤って「落ちた」と感じる
・再試験は不可、別の手続きが必要になる
・対策は可能なので、事前準備と生活習慣の見直しが大切
・家族や周囲の協力が非常に重要
不安な気持ちは当然ですが、正しい情報を知り、早めに準備をしておくことで安心して講習に臨めます。
そして、たとえ免許を手放す結果になっても、それを前向きに捉えることが、これからの生活を豊かにする第一歩になるでしょう。